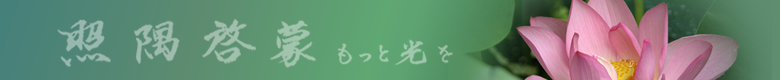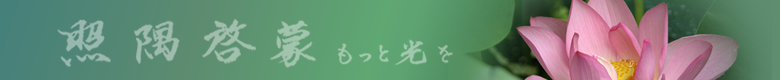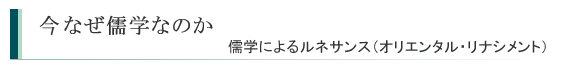
■ 今、中国と日本で儒学(『論語』)は・・・
2008年8月、北京でオリンピックが開催され、世界諸国が集い、中国が文化で彩 [いろど] られました。
開会式第一声 「朋 [とも] 遠方より来る有り、亦 [また] 楽しからずや」 の 『論語』 冒頭の文言が響き、
儒学文化を世界へと誇る演出がなされました。
かつて、”文化大革命”(30年余り前)で強力に弾圧されたことが信じられない位、儒学 (孔子・『論語』や易学) 思想が
復活再生 [ルネサンス] されつつあります。
今、中国の子供・若者たちは 『論語』 を学んでいます。
日本でも ”静かな 『論語』 ブーム” とマスメディアが報じ、書店では ”論語”の2文字をタイトルに入れた本が多く並ぶようになりました。
孔子の学・「儒学」 の必要性が見直されているという兆 [きざし] が感じられます。
さて、”日の出ずる処 [ところ] =アジア” がすぐれた文化圏として結ばれていた時代が幾たびかありました。
”儒学文化圏” と称することも出来ると思います。
その交流は、例えれば、中国を父母とし朝鮮・日本を兄弟姉妹とするようなものでした。
大東亜戦争終了後、アジアの現代史は各国が独自の途 [みち] を歩んでいます。
近未来の世界は米・中の2大国がリーダーシップをとるでしょう。
今でも13億の人口を擁 [よう] し広大な国土を持ち、また歴史文化豊かな中国。
その中国と ”一衣帯水 [いちいたいすい] の地” にある我国は、今後どのような交流をしてゆくべきなのでしょうか。
■ 西洋と東洋のルネサンス(=リナシメント)について・・・
ところで、ルネサンス(文芸復興・再生)は、14世紀 イタリア・フィレンツェに発祥し
ヨーロッパ全土に波及した古典文化(ギリシャ・ローマ)の復活再生運動です。
すなわち、中世の”神(仰)の時代”は、文化的に真っ暗で ”暗黒時代” と称され、
人間性(ヒューマニズム)が死に絶えました。それが生き帰るのがルネサンスです。
ここで注目したいのは、イタリアルネサンス=リナシメントは単なる古代の再生ではなく、
東方文化という当時の新しい要素が加わって興 [おこ] ったということです。
このルネサンスを儒学思想の中に捉 [とら] えてみましょう。
『易経』 の卦に ”地下明夷 [めいい] ” という卦があります。
地中の太陽、明るいもの明らかなものが傷 [やぶ] れ害される。
君子の道塞 [ふさ] がって小人はびこる(”天地否”の卦)でもあります。
日本の『古事記』では、天照大御神 [アマテラスオオミカミ] の”天の盤戸 [いわと] がくれ” です。
ルネサンスは、易卦 ”地雷復 [ふく] ” 、 ”冬来たりなば春遠からじ(シェリー)” で一陽来復、維新です。
大東亜戦争敗戦・米による占領政策実施から60余年を経た現代。
私には、今という時代が、 ” 準暗黒時代=蒙 [もう] の時代” 、易卦にいう
”地下明夷” ・ ”山水蒙” の時代に思われます。
■ 外国から尊敬された、かつての日本人・・・
近代の歴史をよく眺めてみると、かつての日本人は他ならぬ外国人から尊敬されていたことに驚かされます。
F.ザビエルをはじめとする多くの宣教師、駐日米総領事ハリスなど在日外国人が賞賛しています。
幕末の欧米列強も、「日本人は武士(指導者層)は武士道を持ち、婦人・子供も勤勉にして貞淑、徳義があり、
とても植民地化は出来ない。」 と考えました。明治新政府のリーダー達・岩倉使節団がサンフランシスコで尊敬をもって評価された事も記されています。
かつての日本人は、物質的には必ずしも豊かでなくとも、武士から庶民、婦女子・子供にいたるまで、
儒学の徳目(仁義や敬恥など)をよく修め、人間として尊敬を得ていたということです。
■ ”義”でなく”偽”、 ”徳”でなく”(利)得” の今の日本人・・・
今の日本人はどうでしょうか。エコノミックアニマルと蔑称 [べっしょう] されて久しく、
今では、世界で日本人を民族として尊敬する人がどれだけいるでしょうか?
敗戦後60余年のツケは、深刻なものとなってきました。
2007年の世相を表す言葉が ”偽” でした。
儒学の ”義” (よい、おおやけ、社会的使命) に変わって、
”偽” (うそ、いつわり、あざむき)がまんえんし、”徳” に変わって自己中心の ”(利)得” を追いかけるようになってしまいました。
各界で、徳あるトップ(長)が少なくなってまいりました。政界において、政治家の器や倫理が問われています。
儒学は、政治と倫理道徳が合一の、修己治人 [しゅうこちじん] の教えです。
優れた指導者(リーダー)を持てない国民は何と不幸ではないでしょうか。
財界においては、成果主義・拝金主義が支配し、経営者は ”利に放 [よ] りて怨 [うら] み多く” (『論語』)
その企業倫理が問われています。
本来、”経済” の語は、福沢諭吉が ”経世済民 [けいせいさいみん] ” から訳したものです。
明治の渋沢栄一、昭和の松下幸之助等、儒学精神にのっとった立派な経営者が時代を先導しました。
平成の経営者はどうでしょうか?
教育は国家100年の計であり、我々の未来そのものです。
敗戦後、教育者の権威は失墜 [しっつい] し荒廃してきました。
近年の教育行政自体の不祥事が露見するに到って、教育はどこへ向かって行けば良いのか混迷の状態です。
■ 今こそ儒学によるルネサンス オリエンタル・リナシメント オリエンタル・リナシメント
過去の理想郷(ユートピア)を再現しようとするのは、東洋人の特徴でもあります。
”孔子一貫 [いっかん] の道” は ”周” の再建でした。
その孔子は ”仁” (おもいやり・いつくしみ) を説き、”敬” を強調し、続く孟子は 仁 に ”義” (おおやけ、社会的使命)を加え ”恥” を力説しました。
今の日本は、偽にみち ”信” なく、親子に ”孝” なく、礼 (あいさつ、マナー) なく・・・
心の蒙 [くら] い時代となりました。
儒教哲学的に言えば、陰陽のバランスが崩れ、陽に偏向して、中庸(中和)を欠いている時代です。調和状態をとり戻さねばなりません。
そのバランスを取り戻そうとする、儒学の復権から復活の兆 [きざし] もあります。
例えば、儒学・東洋思想の源である陰陽(五行)説は、明治の西洋崇拝思想で軽視されてきましたが、
ようやく見直され復権しつつあります。
西洋医学に対する漢方、中国医療も同様です。
卑近な例をあげれば、和食がハンバーガー等の洋食にとって変わられましたが、今再び和食が見直され外国でも評価されています。
”和” の復権・回帰です。
今、各界で長(トップ)から一般国民にいたるまで、
老若男女 [ろうにゃくなんにょ] 、本 [もと] に立ち帰ることが急務です。
忘れられ、なえがしろにされているものをとり戻さなければなりません。 誰もがすっかり忘れてしまう前に!
”徳” のともしびを絶やしてしまっては終わりです。 未来はありません。 亡びぬようにと国と国民をしっかりとつなぎとめておく ”根株” は、
道徳・徳義とその教育に他ならないのです。 誰もがすっかり忘れてしまう前に!
”徳” のともしびを絶やしてしまっては終わりです。 未来はありません。 亡びぬようにと国と国民をしっかりとつなぎとめておく ”根株” は、
道徳・徳義とその教育に他ならないのです。
「温故知新」(『論語』)。アジアが平和に交流し、新しい時代の息吹 [いぶき] を吹き込みつつ、
儒学に代表される優れた文化で再生(儒学によるルネサンス)し、
”オリエンタル・リナシメント(東洋の文芸復興)”が実現することを望みます。
そして、我が国の持つ ”当鋳力 [とうちゅうりょく] ” (優れた受容吸収能力) が発揮され、
日本的リナシメントによって、徳が形をとった ”美しい国” が再現されることを望んで止みません。
■儒学からの言霊
■儒学随想
■文献渉猟
■高根講演録
■大難解・老子講
【参考】
【 関連ページ 】
|