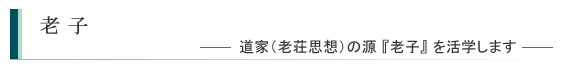

儒学と老荘(黄老・道家)思想は、東洋思想の二大潮流であり、
その二面性・二属性を形成するものです。
国家・社会のレベルでも、個人のレベルでも、儒学的人間像と老荘的人間像の2面性・2属性があります。
また、そうあらなければなりません。
東洋の学問を深め つきつめてゆきますと、行きつくところのものが、“易”と“老子”です。
―― ある種の憧憬 [あこがれ・しょうけい] の学びの世界です。
東洋思想の泰斗・安岡正篤先生も、次のように表現されておられます。
「東洋の学問を学んでだんだん深くなって参りますと、どうしても易と老子を学びたくなる、
と言うよりは学ばぬものがないと言うのが本当のようであります。
又そういう専門的な問題を別にしても、人生を自分から考えるようになった人々は、読めると読めないにかかわらず、
易や老子に憧憬 [しょうけい] を持つのであります。」
( 安岡正篤・『活学としての東洋思想』所収「老子と現代」 P.88引用 )
このたび、定例講習・「孝経」の講座を修了し、「老子」を開講することとなりました。
担当講師の私(髙根)は、50代にして、『論語』・『易経』に『老子』をあわせて講じることに、
教育者としての矜恃 [きょうじ] を新たにしているところです。
『論語』・『易経』とともに、『老子』の影響力も実に深く広いものがあります。
『老子』もまた、言霊の宝庫なのです。我々が、日常、身近に親しく使っている格言・文言で『老子』に由来するものは、
ずいぶんとたくさんあります。例えば、次のように枚挙にいとまがありません。
- 大器晩成 (41章)
- 和光同塵 [わこうどうじん] (4章・56章)
- 無為自然 (7章)
- 道は常に無為にして、而も為さざる無し (37章)
- 柔弱謙下 [じゅうじゃく/にゅうじゃく けんか] の徳 (76章)
- 柔よく剛を制す (36章)
- 小国寡民 (80章)
- 天網恢恢 [てんもうかいかい] 、疏 [そ] にして失わず〔漏らさず〕(73章)
- 千里の行 [こう/たび] も、足下より始まる (64章)
- 知足(たるをしる) / 知止(とどまるをしる) (33章・44章・46章)
- 上善若水 [じょうぜんじゃくすい:上善は水のごとし] (8章)
- 天は長く地は久し (7章) cf.“天長節”・“地久節”の出典
- 知る者は言わず、言う者は知らず (56章)
- 大道廃 [すた] れて、仁義あり (18章)
- 怨みに報いるに徳を以てす (63章)
- 禍 [わざわい] は福の倚 [よ] る所、福は禍の伏す所 (58章)
ところで、(孔子とは対照的に)老子という人物は、実は、いたかどうかもはっきりしないのです。
が、少なくとも 『老子』(『老子道徳経』) と呼ばれている本を書いた人(人々?)は、いたわけです。
時代的には、儒家が活躍したのと(諸子百家の時代、春秋時代〔BC.770~BC.403〕の末頃から)、
同時代か少し後の時代と考えられます。
そして、近年この『老子』に、歴史的な新発見があったのです!
『老子』の現存する最古のテキスト=今本 [きんぽん] 『老子』というものは、8世紀初頭の石刻でした。
ところが、1973年冬、湖南省長沙市馬王堆 [ばおうたい] の漢墓で、帛〔はく:絹の布〕に書かれた 2種の『老子』が発見されました。
“帛書老子”甲本(前漢BC.206年以前のもの)と乙本(BC.180年頃までに書写されたもの)です。
さらに驚くことに、1993年冬、湖北省荊門市郭店の楚墓から、『老子』の竹簡 [ちくかん] が出土しました。
この“楚簡老子”は、“帛書老子”よりさらに 1世紀ほど遡るBC.300年頃のものです。
こうして、『老子』のテキストは、一気に1000年以上も前にまで遡って、
我々の目にするところとなりました。これ等の研究により、老子研究の世界も、歴史学や訓詁 [くんこ] 学のそれのように、塗り替えられ新たになろうとしています。
新発見の具体的一例をあげれば、「大器(ハ) 晩成(ス)」があげられます。
国語(現代文、古典ともに)で、しばしば登場する文言です。
四字熟語としても、小学生・中学生のころからお馴染みのものですね。
“大きな器 [うつわ] は夜できる”という珍訳が有名ですが、大きな器を作るのには時間がかかるという(それだけの)意です。
そこから敷衍 [ふえん] して、立派な人物は速成では出来上がらず、晩年に大成するという意味で用いられます。
即戦力が求められ、レトルト食品なみの速成(即製)人間を作りたがるご時世。心したい箴言 [しんげん] ではあります。
ところが、この「大器晩成」は「大器免成」が本来の意義であったのです。
真に大いなる器(=人物)は完成しない、完成するようなものは真の大器ではないということです。
これこそ、老子の思想によく適うというものです。
( → ※詳しくは、髙根ブログ【儒灯】・《「大器晩成」と「大器免成」》をご覧ください。)
―― 『論語』の中に、孔子の「温故而知新」(故 [ふる/古] きを温 [あたた/たず・ねて] めて新しきを知れば、
以て師となるべし)の名言があります。
“帛書老子”・“楚簡老子”の新発見による研究成果も踏まえながら、20世紀初頭、平成の現代(日本)の“光”をあてながら、
「老子」と“対話”してまいりたいと思います。故 [ふる] くて新しい「老子」を活学してまいりたいと思います。
なお、主要テキストは、原典の書き下し文・訳も含めて、すべて私(髙根)のオリジナル教材を用います。
※本講座 老子[1]~老子[50] は第82回定例講習にて終了いたしました。
下のボタンをクリックすると、内容をご覧いただけます。
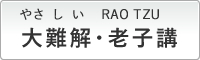
【 関連ページ 】
|

