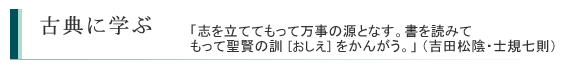
私達は、古典を学ばなければなりません。古き良き書を熟読することで 「志 [こころざし] 」 も創られてまいります。
『論語』 の中で 孔子は 「故 [ふる] きを 温 [たず] ねて (温 [あたた] めて)
新しきを知れば、以て師となるべし」 (為政) と言っています。
また、「述べて作らず、信じて古 [いにしえ] を好む」 と。
身近に例えてみますと、”カレー” をねかせて、また 一味加えて温めると素敵においしくなるようなものです。
また、EH.カーという歴史(哲学)家が 「歴史とは、過去と現在との対話である」 (『歴史とは何か』) と述べています。
私達が学ぶ古典は、単に過去の知識を吸収するのみでなく、現代の光に照らして、更に未来を展望しての学びでなければなりません。
古典の現代的意義を考えるという意味で、古典は(いつの時代も)常に新鮮といえます。
それが古典を活 [い] かすことであり、真の意味での ”再生(ルネサンス)” です。
学問的にいえば ”活学” です。
なお、学習法について、孔子が ”音楽” を非常に重視していたこと、
我国では 以前は ”素読 [そどく] (=音読)” を大切にしていて
有効であったことをつけ加えておきます。
【四書五経 [ししょごきょう] 】
さて、儒学の中心的テキストブックを ”経書 [けいしょ] ” と称します。
織物で経 [たて] 糸が重要だからでしょう。
具体的には 四書五経が中心です。
時代の指導者(エリート) たらんとする人の必修教養であり、
また官吏 [かんり] (=公務員) 任用制度の試験科目・範囲でもありました。
現代の (国立)大学入試科目をイメージするとよいでしょう。
【 関連ページ 】
|

